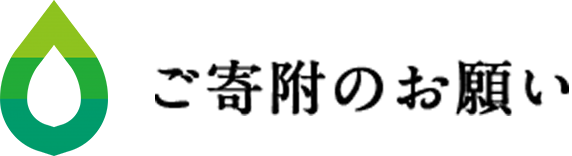R6年度 12/22高大連携フォーラムin京都大学(2024年12月22日開催)
2025.03.04
- 大学院受験生・研究者の方へ
- 一般の皆様へ
- 在学生・卒業生
2024年12月22日、京都大学にて、「R6年度 12/22高大連携フォーラin京都大学」と題して、高校生によるポスター発表と高校生・大学生の交流会を実施しました。
本フォーラムは、2011年度から毎年開催していた「瀬戸内海の環境を考える高校生フォーラム」を引き継ぐイベントです。このフォーラムは、海をフィールドとして探究している高校生たちの情報交換の場として開催されてきました。2018年度からは、従来の取り組みに「地域」「防災」等のキーワードが加わった発表、2021年度からは、「海と山のつながりを考える」をテーマに発表がなされるようになりました。
例年に引き続き、今年度も高校生によるポスター発表と、大学生と高校生の意見交換会が行われました。ポスター発表では、これまでの探究の成果を他校の人に精一杯伝えるとともに、鋭い質問に対して自分なりの言葉で受け答えする姿が印象的でした。大学生から高校生に対しては、研究テーマの選定やその背景・研究の構造に関する質問が多く寄せられました。「なぜこのテーマを選んだのか?」「研究の目的をどう設定したのか?」といった問いかけを通じて、高校生が自身の研究を振り返る機会となっていました。また、発表内容が大学レベルに匹敵する高度なものであったことから、先行研究との比較や方法論の妥当性についても具体的な指摘が行われ、議論が深まる場面が多く見られました。
さらに、大学生は自身の研究経験を基に、高校生の発表に対して「大学での研究で課題となる点」や「高校の段階でさらに掘り下げて欲しいポイント」について具体的な意見を共有するなど、実りある意見交換が行われました。このような質疑応答を通じて、高校生は自身の研究を改めて見直す機会を得るとともに、探究の意義を再確認する貴重な時間となっていました。
また本サミットは、教職科目を履修している大学生にとっても、日々の大学生活を内省し、探究的な活動の先駆的な事例を学ぶことができる良い機会となりました。
なお、当日の高校生のポスター発表の内容は下表のとおりです。
|
高校名 |
発表概要 |
|
兵庫県立尼崎小田高等学校 |
「大阪湾阪神地域の魚類に含まれる MP」 「尼崎におけるBODおよびCODでの水質調査」 「マメ科の同科異属接木は可能なのか」 「昆虫病原糸状菌を用いて蚊から人を守る殺虫剤の開発」 「海洋とプラスチック関連性と、プラスチックについて知ったこと」 「海ごみを減らせるか?」 「災害時要配慮者の支援と地域コミュニティづくり」 「フードドライブの必要性」 「海洋植物プランクトンの培養・観察」 「近畿産チチブ類の集団遺伝的構造」 「尼崎産セミ類の抜け殻調査」 「大阪湾のプランクトン観察 ―尼崎運河と大阪湾の比較―」 |
|
神戸市立六甲アイランド高等学校 |
「光合成における電流の影響について」 |
|
兵庫県立御影高等学校 |
「キノコ由来カタラーゼの活性比較」 「六甲山と神戸の海のつながりを考える」 |
|
兵庫県立星陵高等学校 |
「神戸市垂水区の山田川でベニトンボを発見!」 |
|
兵庫県立農業高等学校 |
「地域の未利用資源の有効活用」 |
|
兵庫県立姫路西高等学校 |
「海面水温と降水量の関係性」 |
|
山陽学園中学校・高等学校 |
「ICTが変える海洋ごみ問題の解決への未来」 |
|
広島県立広島国泰寺高等学校 |
「シマミミズにおけるマイクロプラスチックの影響」 「高水温がスサビノリの色落ちに与える影響」 「ダンゴムシの食の選択」 「デュビアの成長と繁殖概要」 |
参加した高校生・大学生から寄せられたコメントの一部を紹介します。
○高校生
・ポスター発表では京大生から貴重の意見を聞くことができ、ディスカッションでは、他校の人と交流でき楽しかったです。
・今回のフォーラムを通じて、自分の研究の問題点がまた新たに分かった。ディスカッションでは、コミュニケーション力やまとめる力が足りないと感じた。この経験を活かし、今後も研究を行っていきたい
・大学生や院生からの質問によって、自分の探究の内容に足りなかった部分を知ることができた。
・考えの違う人たちと意見をまとめて発表することはなかなかない機会で面白かった。
・大学生や他校の生徒・先生と意見交換をしたり、アドバイスをもらったりととても刺激になった。今後の自分の課題研究を進みやすくすることができた。研究を多角的に深く考えることができた。
○大学生
・とてもレベルの高い発表に驚きました。質問にも即座に丁寧に対応していて、深く調べられているのが伝わりました。
・先行研究をきちんと調べられていたり、統計的な知見に基づいたり、探究の発想が面白かったりととてもレベルの高い探究が行われていて、素晴らしいと思いました。
・どの探究テーマも興味深く、今後の展望と社会への還元が見据えられた発展的な探究で面白かったです。
・学校で教育の一環として研究の場を設けて貰うことは非常に恵まれていることだと思うので、研究を通して学んだことをこれからの学習に活かして欲しいと思います。
・先行研究と対比した探究の位置づけ、アンケート調査の妥当性などは、大学に入学してから指摘されることでもあるので、高校生のうちから意識することで、高校、大学でもより発展的な研究になるのではないかと思います。
・普遍的なテーマではなく、自分達の周辺から研究課題を設定し、尚且つ専門的な機材を用いて学術的に探求されており、学会レベルの発表であると感じました。また、専門外の自分にも理解できるよう、言葉を尽くして分かりやすく説明して下さり、とても楽しく拝聴させていただきました。
・主体的に取り組まれている姿に刺激を受けました。バイオ系の研究が多かったですが、大学に入れば自分の知らなかった学問に沢山出会うことになります。自分を縛らず、学問の枠組みを超えて思うままに知的好奇心を満たす研究をしていってほしいと思います。
当日の会場設営や運営については、兵庫県立尼崎小田高等学校の生徒の皆さんと先生方を中心に担当していただきました。素晴らしい発表をしてくださった高校生の皆さん、各校の先生方、積極的に参加してくださった大学生の皆さんに、この場をお借りして、改めて感謝申し上げます。